【完全網羅】戦災や大災害時に本当に必要なものと防災知識
日本を取り巻く危険
日本の周辺国には核ミサイルを持った危険な国が多くあり、日本も核戦争に巻き込まれるのではないか、近い将来、大規模災害が日本を襲うという話を聞いたことが無いでしょうか?
実はこれらの話は、近々、現実に起こり得る可能性のある話なのです。
戦争については「ロシアによるウクライナへの侵攻」があり、「中国による台湾侵攻」、「北朝鮮によるミサイル攻撃」などが危険視されています。
台湾侵攻というとあまり危険と感じないかもしれませんが、日本には米軍基地があるためミサイル攻撃される可能性が高いと言われているのです。
災害については「東日本大震災」があり、将来、「南海トラフ巨大地震」や「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震」、「富士山の噴火」があるのではないかと言われています。
そのため日本政府も危機感を持ってこれらの将来の戦争や災害への対策を推進している状況となっています。
つまり日本政府がこれらの話は眉唾ではないと言っているのです。
戦争や災害が起きたときにどう備えるかで、あなたやあなたの家族・大切な人の「生存率」が変わってきます。
ロシア・ウクライナ戦争でのウクライナの惨状、ロシア軍の残酷さ、東日本大震災での悲惨さはテレビなどで放送されていますが、適切な知識と備えがあればそれらの危険から身を守る助けとなり、「生存率」がグッと上がるでしょう。
もし戦争や災害に遭遇したら、「水」、「食料」、「電気」、「医療品」、「拠点」、「トイレ」、「防暑・防寒対策」など様々な状況への備えが必要です。
戦争への備えはそのまま災害への備えにも利用できます。
あなたやあなたの家族、そして大切な人を守れるようにしっかりと備えておきましょう。
大地震での経験
私自身、大地震を経験したことがあるのですが、外に出ると信号は倒れ、亀裂が走って寸断されている道路がありました。
スーパーやコンビニは停電で暗くなっており、開店してるのかしてないのかすら分からない状況でした。
中に入ってみると飲料がすでに無く、500mlのあまり人気のないお茶類や野菜ジュースなどが残っているだけでした。
カップ麺などのインスタント食品も激辛味しか残っておらず、トイレットペーパーなども無く、キチンペーパーやクッキングシートなどが少し残っているだけでした。
幸いにも家は無事で、停電と断水は免れました。
ですが、ガスは安全のために止められ使えなくなり、料理の時に慌ててカセットコンロとホットプレートを探したのを覚えています。
水道からは薄茶色の水が出てしばらく流しても色が消えなかったため、料理や飲料水に使うのは諦め、代わりに家にあった数本のペットボトル天然水を使いました。
家も無事で小売店への物流は地震の被害があったルートとは別ルートで届けられたため、私の住んでいる地域は数日でほぼ通常通りの生活に戻ることができましたが、被害が大きい地域は家が倒壊するなどし避難生活を余儀なくされていました。
地震発生時点では家の安全確認と周囲の状況の把握、物資の調達で手一杯でした。
ですが落ち着いてきた時、水の備蓄が少ないことに気付き、浄水器などを持っていなかったため、料理や飲料として使える水が果たして足りるのかに不安を感じていたのを覚えています。
恐らく、断水と停電にも見舞われた場合、もっと大変なことになったと思いますし、家が倒壊して避難生活となった場合、不安しかない状況になったのではないかと思っています。
本記事はその時の経験と趣味の登山での経験、戦争に関する知識を元にして書かれています。
1、水の確保

内閣府による首都直下地震等による東京の被害想定によれば、上水道の復旧目標日数は30日となっています。
つまり断水となった場合、地域によって早い遅いはありますが30日は水道が使えないと考えてください。
2011年に起きた東日本大震災の時は水道の復旧までに24日間かかったと言われています。
断水期間は水道無しで乗り切るしかありませんし、戦争などによってより長期間使えなくなる可能性もあり得ます。
水の確保は「生存」における最重要事項です。その時の備えはしっかりとしておきましょう。
飲料水の備蓄
農林水産省は最低「3日分」、できるなら「1週間分」の飲料水を備蓄しておくことを推奨しています。
ですが道路の寸断などで地域が孤立してしまった場合など様々な状況により、復旧が遅れてしまった場合、1週間分では全く足りません。
この3日~1週間分の飲料水は、将来にわたる飲料水確保の目途を立てる時間を得るための水だと考えてください。
常備水は「市販されているペットボトル飲料水」、「ウォーターサーバー」などが考えられますが、もし「ウォーターサーバー」を常備水として検討するならサーバー無しでも簡単に水を使うことのできる企業の商品を選ぶことをお勧めします。
もし「ペットボトル飲料水」を常備水とするなら、スペースを取らずに多くの水を保存することができる2リットルペットボトルと周囲を探索するときに役立つ500mlペットボトルの2種類を備蓄しておくといいでしょう。
500mlペットボトルは空になっても役に立ちます。
◎保存水 備蓄用 2リットルペットボトル
◎保存水 備蓄用 500mlペットボトル
これらの保存水は長期にわたって保存可能です。
2リットル×6本、500ml×24本はおよそ成人1人あたり3日~5日分の水に相当します。
あなたの家族の人数分準備しておきましょう。
浄水器
これは備蓄水でも足りず、長期間に渡る飲料水の確保が必要になった場合を想定しています。
浄水器はお風呂の水や川の水などを飲料水に変えてくれる物です。
浄水器があればフィルターがある限り飲料水の確保が可能となりますし、長期間に渡って水の心配をしなくて良くなるため、飲料水の安定的な確保の目途をより長く得ることができるでしょう。
アウトドアやサバイバルで使用する「フィルター交換型の携帯用浄水器」がおすすめです。
「使い捨て型」もありますが、「使い捨て型」はあれば助かる程度と思っておけばいいと思います。
◎充電式高機能携帯浄水器「Greeshow GS-2801」
◎「Greeshow GS-2801」交換用フィルター(内蔵用)
◎「Greeshow GS-2801」交換用フィルター(外付け用)
「Greeshow GS-2801」は、水中の不純物はもちろん、細菌やウィルスも99.999%除去する充電式携帯浄水器です。
モバイルバッテリーからも充電可能で、フィルター交換も半年に一度(使用頻度によります)でメンテナンスも楽な製品です。
避難生活となると使用頻度が上がるため、フィルターも各2個づつ用意しておいた方が安心です。
モバイルバッテリーからも充電可能ですが、電源が無い時は使えないですので注意が必要です。
◎高耐久手動携帯浄水器「ミニワークスEX」
◎「ミニワークスEX」用フィルターカートリッジ
◎「ミニワークスEX」用メンテナンスセット
「ミニワークスEX」はNSFプロトコルP231のバクテリアと原生動物を取り除く基準をクリアしており、効率的にきれいな水が得られます。
ウイルスには対応していません。
手動ポンプ式ですので、どこでも使用できます。
メンテナンスキット付属の洗浄用具でフィルターを洗浄すればより長持ちしますし、パッキン交換も可能です。
何かあった時のためにフィルター2個とメンテナンスキットがあれば安心でしょう。
湧き水の利用
近くの山などに湧き水がある場合、その場所を覚えておきましょう。
ウォータータンクやペットボトルに入れて家や拠点に持ち帰ることもできます。
私自身、被災した時、山に汲みに行こうかを検討しました。
そのまま飲める湧き水だとしても、家や拠点に持ち帰った場合は安全のために煮沸をしてから飲むことが大切です。
そして戦争や災害発生時には混雑することが考えられますので、湧き水のみに頼ることはやめた方がいいでしょう。
あなたしか知らない湧き水でないなら、あくまでもより長く生存するための補助的な給水手段と考えておいた方がいいと思います。
給水車の利用
戦争の場合は給水車が来るかどうかはわかりませんが、災害があって断水した場合、給水車がその内やってきます。
給水車の水は、ウォータータンクやポリタンク、ペットボトルなどに入れてもらって持ち帰ることをお勧めします。
ペットボトルの場合は、運べる量も限られますがリュックに入れて運ぶことができます。
ウォータータンクやポリタンクの場合は重いため、お年寄りや女性、子供の場合、折り畳み式の台車などがあると便利です。
だた給水車の数が少なすぎると言われているため、大規模災害などの場合、かなり遅れてやってくることも予想されますので、飲料水の備蓄は多めにしておきましょう。
◎貯水バッグ
柔らかい素材でできた貯水バッグです。
折りたたむことができるため、保管場所に困りません。
ですが、ポリタンクと比較すると穴が開きやすいです。
◎ポリタンク(コック付き)
ポリタンクは強い衝撃を与えない限り壊れにくい素材でできています。
20リットルの大容量を貯水でき、コックが付いているため家に持ち運んだらそのままテーブルやカウンターなどの上に乗せて簡単に水を使うことができます。
ですが、それなりの大きさのため使わないときは置き場所に困ることが多いでしょう。
◎ミニキャリー
台車は給水場所が遠い場合や何か重い物を運ぶときに活躍します。
ブレーキ付きなので坂道でも安心して運べますし、折り畳み式なので、ちょっとした隙間に立て掛けて保管しておくことができます。
雨水の利用
雨水は長期的に水の確保ができない状況の場合に非常に重要になります。
清潔な器に保存すれば煮沸して飲むことができますし、体を拭くための水や食器や衣類などを洗うための水、トイレの水としても利用できます。
そのため、少し大きめのバケツやタライ、じょうご(漏斗)、じょうごに合うプラスチック製容器などを用意しておくといいでしょう。
もし本格的に備えるなら、雨水タンクを設置すると効率良く雨水を集めて使用することができ、市町村によっては補助金もでるためおすすめです。
雨水タンクの水はガーデニングの水や玄関や家の外側の掃除をするときに使う水、洗車などでも利用できるため、断水していない時でもあると便利ですし水の節約にもなります。
◎雨水タンク
こちらの雨音くんはドレン口が付いているためメンテナンスがしやすく、オーバーフロー対策などもされているためおすすめです。
川の水の利用
よほど上流の川でない限り川の水は雨水よりも汚く、下流に行けば下流に行くほど汚くなっていきます。
そのためよほど上流でない限り川の水を使う場合はろ過が必須です。
においや濁りの程度にもよりますが、ろ過すれば雨水と同じく体を拭くための水や食器や衣類などを洗うための水として利用できますし、煮沸すれば飲み水にもなります。
ですが、ろ過してもにおいや濁りが強い場合、トイレの水として使いましょう。
2、食料の確保

保存食の備蓄
戦争や災害となった場合、スーパーなどは混雑して在庫はほぼなくなり、食料が確保できなくなるものと想定されます。
そのため食料も飲料水と同じく備蓄が大切です。
農林水産省は最低3日~1週間分、できるなら2週間分の食料を備蓄しておくことを推奨しています。
これは水と同じく道路の寸断などで配送車が通行できなくなった場合など様々な状況により、食料の供給が遅れてしまう可能性が大いにあり得るからです。
もし長期に渡って食料を得ることができなくなると想定される場合においても、食糧確保の目途を立てる時間を得ることができます。
備蓄食料は長期保存ができるものを選びましょう。
米、パックご飯、乾麺(そば、うどん、パスタなど)、カップ麺やみそ汁などのインスタント食品、レトルト食品(カレーは牛丼の素など)、パスタ用ソース、缶詰(缶切りもセットで)、日持ちする野菜(いも類、玉ねぎなど)、調味料(砂糖、塩、しょうゆ、ソースなど)、調理用油、パックジュース、お菓子などが候補として上がります。
米やカップ麺などはもちろん大切ですが、暖かいものや甘いものはストレスを軽減させてくれる効果がありますので、飴やチョコレート、クッキーやビスケットなども備蓄しておくといいでしょう。
もし食料の供給が長期にわたって滞り見通しが立っていない場合、あなたのストレスは計り知れないものとなっていると思います。
水や食料を備蓄する時は、保存したままにして置くのは賞味期限などを忘れることもあり危ないですので、日頃から使いながら保存しておくローリングストックが簡単なものを選びましょう。
主食
◎無洗米
災害時は空けても虫が付きにくいチャック付きの袋になるべく小分けに保管しておいた方が安全です。
そして無洗米は水の節約になるためおすすめです。
精米2㎏で成人1人あたりおよそ10日分(お茶碗30杯分と計算)となりますので、家族の人数分用意しておけば、10日分のお米には困らないでしょう。
半年くらい経ったら新しいものを購入して以前に購入したものを食べるなどすると無理なくローリングストックができます。
2㎏と軽く、そのまま持っていけるためキャンプなど野外でお米を炊く時にも便利です。
◎極細パスタ
般社団法人日本パスタ協会によると、乾燥パスタの賞味期限は未開封の状態で製造後約3年とされており、長期保存に向いているため備蓄食として保存できます。
簡単に調理でき、色々な種類のパスタソースを用意しておけば、飽きづらくなります。
しかも極細パスタの場合は、水の節約のために茹でるのではなく水に漬けて戻す場合、芯まで浸透する時間が短くなるのもメリットです。
乾燥パスタ500gで成人1人あたりおよそ3日~5日分となりますので、500g×3袋を家族の人数分用意しておけば、約10日~15日分の食事には困らないでしょう。
◎その他
主食に関してはその他、あなたの好きなカップ麺などを用意しておきましょう。
カップ麺はお湯を注ぐだけで調理でき暖かいスープ代わりにもなるため、寒い冬の日に食べるとホッとします。
普段カップ麺を食べない方も、3ヶ月に1度、家族でカップ麺パーティーを開くなどすればローリングストックもやりやすいでしょう。
上記の米とパスタがあれば2日~3日分ほどで十分でしょう。
主菜
◎レトルト食品(ご飯にかけるもの)
レトルトカレーや丼物はご飯にかけるため、使う食器が少なく水の節約になります。
手軽に調理できるので便利です。
◎レトルト食品(肉や魚)
魚は骨まで食べられるものだと栄養も摂れ、ゴミが少なくなるため衛生的にもおすすめです。
種類が多いと飽きが来にくくなります。
肉を食べると力が付くため、何か作業した時に肉料理があるとうれしいです。
◎パスタソース
こちらは6種×2袋入りで12食分のパスタソースです。3日分となりますので、日数換算でパスタの量と同じくらいの量を備蓄しておきましょう。
パスタも普段食べながら補充するローリングストックがおすすめです。
◎缶詰
食品の保存には期限があるため、普段使いしながら新たに買って補充する「ローリングストック」が大切です。
普段から缶詰を使うという人は好きな物を選んでローリングストックができますが、「シーチキン」くらいしか使わない人にとっては買ったらそのまま保存して、中には期限が切れても忘れてる人もいるかもしれません。
こちらの製品は一例ですが、缶詰を普段使わない人は少し高級な缶詰を買って1ヵ月に1度ないし2ヶ月に1度食べる程度の缶詰があってもいいかもしれません。
レトルト食品で代用可能ですので、無理に缶詰を備蓄する必要はありません。
ただ、缶詰は持ち運びが簡単だということと、外装が丈夫というメリットがありますので、あったら助かることは確実です。
そして缶切りを忘れないようにしましょう。
災害時は缶切りが含まれているキャンプ用万能ナイフが便利です。
万能ナイフを選ぶなら、すぐに壊れないしっかりとしたものを選びましょう。
副菜
◎おかずの缶詰
こちらの製品は「きんぴらごぼう」、「切り干し大根」、「ひじき煮」などの副菜の入った缶詰です。
主食・主菜・副菜×2・汁物が栄養バランスが偏らないと言われています。
36缶分は朝・昼・晩の3食とも副菜×2を食べるなら成人1人あたり6日分ですが、恐らくそんなに食べないと思われますので、もっと長く食べ続けられると思います。
◎スープなど
暖かいスープは寒い冬の日にあると暖をとれるのと同時に心を安定させてくれる効果があります。
そして水分補給にもなるため、数日分備蓄しておくといいでしょう。
あなたの好きなものを備蓄しておくと災害時のストレスも軽減してくれるでしょう。
主食=主菜>副菜>汁物が食料備蓄の優先順位ですので、こんなにたくさん備蓄しておけない、もしくはローリングストックがつらいという方は、優先順位に従ってあなたが可能な分だけ備蓄しましょう。
普段から近隣の農家さんの農産物を購入する

これは食材を購入するチャネルを複数持つことと、生産者と繋がるためのコネクションを持つことの2つを意味しています。
食材を購入するチャネルがスーパーなどの小売店のみだった場合、小売店の在庫が尽きてしまったら購入することができなくなります。
そのため米や野菜などの生産者が近くにいる場合、直販しているかどうかを確認してみるといいかもしれません。
戦争や災害のない時から農家さんたちと繋がっていると、もしかしたら優先して販売してくれるかもしれませんし、味は同じだけど形が悪いなどの規格外品も紹介してくれるかもしれません。
支援物資を利用する
戦争や災害となった場合、被害を受けた地域に対し、国内外問わず支援物資が届けられるでしょう。
その支援物資を受け取るためには情報が必要となるため、最寄りの避難所やテレビ、インターネットなどで情報を集め、連絡先や場所などをメモしておきましょう。
最初に支援されるものは、毛布、水、食料だと言われています
あくまでも支援物資ですので、十分な量があるとは限らないため、なるべく事前に準備しておきましょう。
自分で調達する
魚釣りが趣味の人は「魚釣り」という選択肢がありますし、山菜や野草採りなどで食材を調達することもできます。
慣れている人ならどこで採れる(釣れる)のか、どの山菜や野草、魚が食べられるのかを知っていますが、経験のない人は全く分からないため、それなりの危険が伴います。
経験のない人は、経験者に付いて行って地道に覚えていくか、自分で探索して少しづつテリトリーを広げていく必要があります。
もし自分で探索する場合は、山菜よりも危険のない野草を探してみるといいかもしれません。
その時に役に立つのが、食べられる山菜や野草、海辺の生き物が載っている図鑑です。
図鑑を見ながら探索しましょう。
通常であれば東日本大震災レベルの大地震の場合でも、支援物資が届いたりボランティアの人達の炊き出しや行政からの配給などがあるはずなので自分で調達するという段階は、かなり危機に瀕しているということです。
◎野草図鑑
◎海辺の生き物図鑑
これらの本は見てるだけでも面白いですし、お子さんと一緒に図鑑を見ながら実際にとったりするのも楽しい図鑑です。
サバイバル時に役立つでしょう。
3、電気の確保
内閣府による首都直下地震等による東京の被害想定によれば、電気の復旧目標日数は6日となっています。
つまり停電となった場合、地域によって早い遅いはありますが6日は電気が使えないと考えてください。
2011年に起きた東日本大震災の時は電気の復旧までに6日間かかったと言われています。
そのため、停電期間は電気無しで乗り切るしかありませんし、戦争などによってより長期間使えなくなる可能性もあり得ます。
停電となった時に電気が使える人と使えない人とでは快適さとその後の「生存」に雲泥の差がでます。
しっかりと準備しておくと安心でしょう。
ソーラーパネル対応ポータブル電源
ポータブル電源とは、家の電源やソーラーパネルから充電して持ち運ぶことができるバッテリーのことです。
スマートフォンの充電はもちろんパソコンや扇風機、定格出力の大きさによってはポータブルIHクッキングヒーターや冷蔵庫などにも使えます。
キャンプなどのアウトドアで使うなら定格出力500W~1,000W、電池容量500Wh~1,000Wh程度の比較的小型のものでも十分ですが、防災目的で使うなら定格出力1,000W以上、電池容量1,000Wh以上であなたが持ち運びできてなるべく定格出力も電池容量も大きなものを選びましょう。
そして停電時に役立つのがソーラーパネルでの充電です。
天候が悪い時はあまり役に立ちませんが、天候のいい時は通常の電源と同じくらいの速度で充電してくれます。
停電が長期に渡ったとしてもソーラーパネルとポータブル電源があれば冬の寒い時期でもIHクッキングヒーターで暖かい料理を作り、ハロゲンヒーターなどで暖をとることもできますし、扇風機やポータブルクーラーで涼を得ることもできます。
戦争や災害に備えるならソーラーパネルとポータブル電源は必需品です。
ただ電池容量が小さかったり使い方によってはほんの数時間で電気が無くなってしまうため、必要最低限の電源と考えてください。
そして普段からソーラーパネルで発電しポータブル電源に充電して使えば電気代の節約にもなりますので、あって困るものでもありません。
◎ポータブル電源とソーラパネルのセット
太陽光発電システムと蓄電池
これは戦争や災害などによる停電時でも家から避難する必要はない場合にあった方がいいものです。
停電時でも自立運転モードに変えれば自立運転用コンセントから電気が使えますし、蓄電池があれば発電した電気を貯めて夜や翌日に使うこともできます。
天気の機嫌次第なところはありますが、スマートフォンやパソコンが使え、家の中で調理でき、暖や涼がとれるなど通常の生活とあまり変わらないのはありがたいことです。
ただ、家から避難しなければならない状況になった場合は使うことができないため、ポータブル電源は用意しておいた方がいいでしょう。
充電池
充電池は電源が無ければ使えませんが、電源さえあれば繰り返し使える便利なものです。
懐中電灯やLEDランプなどの灯り、充電式カイロやハンディファン(小型扇風機)などの暖や涼、スマートフォンへの充電などで使用できます。
乾電池を使う製品はほとんど持ち運び可能な点が重要です。
つまり家や拠点から離れる際にも利用できるということです。
泊りがけで家や拠点から離れなければならないときや、歩いて山などを越えて避難しなければならない事態になった時に活躍します。
そして停電時、LEDランプは家や拠点でも夜に活躍するでしょう。
◎充電池
こちらの充電池は単三電池は2800mAh、単四電池は1100mAhと普通の充電池の2倍以上長持ちするものです。
災害時はできるときに充電する環境かもしれませんので、一度に多く蓄電できる充電池だと充電回数も交換回数も少なくて便利です。
ケース付きなのですぐに持ち出せ、外でも簡単に保管できるため避難時に役立ちます。
◎電池充電器
こちらの電池充電器は単1、単2、単3、単4、9Vのニッケル水素/ニカド電池を充電できます。
電池の充電状況も表示してくれるため便利です。
あらゆる電池保護機能がついており、充電したまま放置しても自動OFF機能もついているため安心です。
4、医薬品の確保

戦争や災害の被害によってはドラッグストアなどで医薬品も在庫切れとなったり手に入らなくなる可能性があります。
そのため「総合風邪薬」、「解熱鎮痛薬」、「胃腸薬」、「処方薬」、「消毒薬」、「虫刺され薬」、「包帯やバンドエイド」、「体温計」などを準備しておくといいでしょう。
大切なのはあなたや家族がいつも使っているもので慣れているものがいいと思います。
処方薬に関しては、通っている薬局に災害時などはどうなるのかを聞いてみるといいでしょう。
もしそれが命に関わるものならなおさらです。
5、食事について
戦争や災害などで電気、ガス、水道が止まってしまった時、どうやって調理して食器をどうやって洗うのかなどで困ることがあると思います。
その際必要なのが調理器具、カセットコンロ、プラスチック製のお皿やコップ、スプーン、箸、割りばし、サランラップ、アルミホイル、ウェットティッシュ、ポリ袋などです。
調理器具は、深型フライパン、ジオ鍋、包丁(サバイバルナイフでもOK)、ピーラー、キッチンバサミ、菜箸(トングでもOK)、おたまがあれば対応できるでしょう。
ピーラーやキッチンバサミは食材を選べばまな板などのない場所でも調理できるため便利です。
菜箸は最悪そこら辺の枝を洗って使ってもOKです。
食器は洗わないで済むようにプラスチック製のお皿やコップにサランラップを掛けて食べるようにしましょう。
そのためサランラップは多めに備蓄しておきましょう。
アルミホイルは調理の際にフランパンなどに敷いて使うと水の節約になりますし、
紙皿や紙コップはあって困りませんが、強度が弱く、汚れるとごみになるため、プラスチック製がおすすめです。
◎深型フライパン
深型フライパンは普通のフライパンと比較して重いですが、焼く・炒める・煮る・茹でる・揚げるの5役をこなせるため、通常時はもちろん避難する時などのあらゆるシーンで活躍してくれます。
ガス、電気プレートコイル、セラミックヒーター、ハロゲンヒーター、電磁調理器(IH 100V-200V)に対応しているため、使用できる熱源の幅も広いです。
注ぎ口が付いており、煮込み料理などを器にそのまま注ぐこともできます。
1~2人の時は20㎝~24㎝のものを、3~4人の時は26㎝~28㎝のものを選ぶといいと思います。
◎ジオ鍋
ジオ鍋は、「ジオプロダクト鍋」の略です。
焼く・炒める・煮る・茹でる・揚げるの5役をこなせるため、通常時はもちろん避難する時などのあらゆるシーンで活躍してくれます。
ジオ鍋は15年保証するほど長持ちし、ご飯もおいしく炊けますので、1~2人ならジオ鍋×2、3人以上ならジオ鍋と26㎝深型フライパン1つづつがおすすめです。
18㎝のものだと3合ほどご飯を炊けます。
◎食器セット(4人用)
野外で食事をする時に最低限必要な食器類はすべて揃っているため、この製品があれば十分でしょう。
実際の製品はもっと緑がかっています。
収納袋が付属しているため、持ち運びに便利です。
ポリプロピレン製であるため121℃までの耐熱性を保持しています。
箸のみABS樹脂製なため、耐熱温度は70℃~100℃です。
箸以外は100℃の熱湯にも変形することなく耐えることができますが、調理などには使わない方がいいでしょう。
普通に食事に使っていればまったく問題ありません。
6、トイレについて
災害時などで自宅のトイレが使えなくなるかもしれませんし、家から避難しなければならない事態になるかもしれません。
トイレが使用できない原因は、停電、断水、排水管のつまり、下水管の破裂などが考えられます。
それぞれの場合に合わせた対処法を知っておくと慌てずに済むでしょう。
タンクトイレ
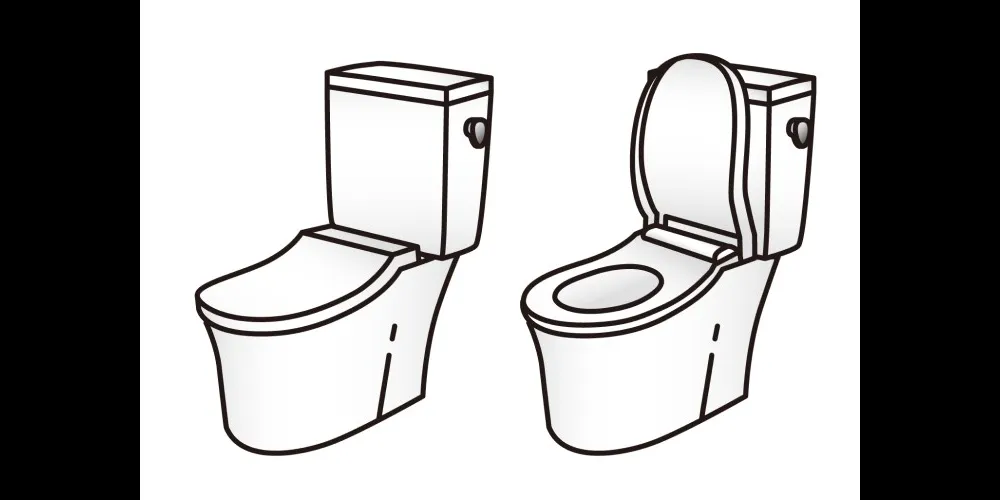
断水時、タンクトイレはいつも通りに使った場合、1回分しか使えなくますが、排水管が詰まったり、下水道が使用できない状態でない限り停電時でもバケツと水さえあれば流すことができます。
水を入れてレバーを引くを繰り返せば流れていきます。
その際、飲料水は使わずお風呂の水や雨水、川の水を使いましょう。
タンクレストイレ
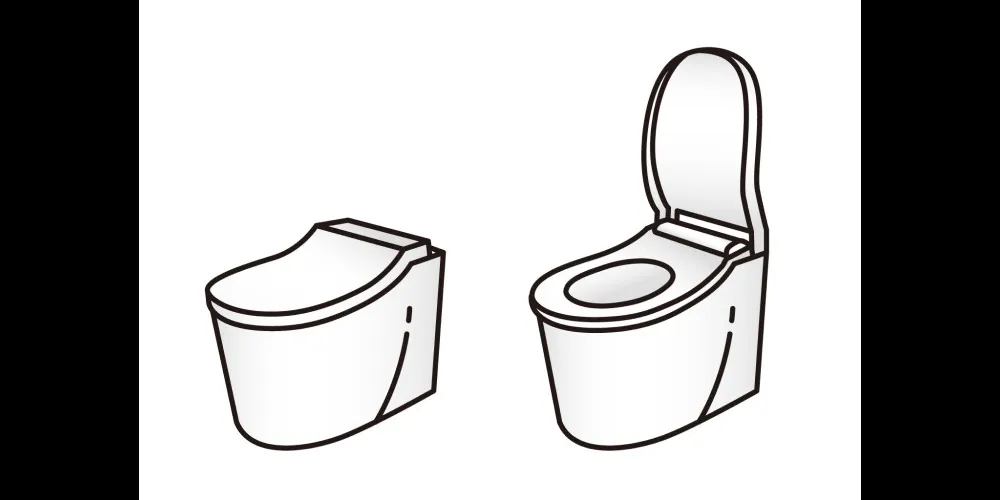
タンクレストイレは排水管が詰まったり、下水道が使用できない状態の時はもちろんですが、断水時、停電時にも使えなくなります。
メーカーによっては便器脇のカバーを開けて乾電池を付けて使えるようになりますし、ほとんどのメーカーでは手動の排水レバーが設けられていますので、タンクトイレよりは面倒ですが、水を入れて排水レバーを引くを繰り返せば流すことができます。
簡易トイレ
災害時に使える簡易トイレには主に2種類あります。
家から避難しなくていい時に使える「便座取り付けタイプ」のものと、避難しなければならなくなった時に使える「組み立て式タイプ」です。
「便座取り付けタイプ簡易トイレ」は、排水管が詰まったり、下水道が使用できない状態になった時に活躍しますし、「組み立て式の簡易トイレ」は野外でも組み立てて使うことができるため、場所を選びません。
「組み立て式簡易トイレ」を使う場合でも「便座取り付けタイプの簡易トイレ」と併用するか汚物専用袋を用意必要があるため、両方準備しておくと安心です。
◎簡易トイレ(便座取り付けタイプ)
こちらの製品は100回分ありますので、1人あたり1日2回使用での交換を想定した場合、1人で50日分、2人で25日分、3人で約16日分、4人で約12日分です。
防臭袋が付属しているため周囲に臭いも漏れませんし、凝固剤があるため固められますので後処理も楽です。
◎簡易組立トイレ
便座がプラスチック製なため除菌ウェットティッシュなどで拭くこともできますし、段ボール製と比較して座り心地がいいです。
そして組立式なので、置く場所に困りません。
トイレのないところで用を足すときに活躍します。
大人用紙おむつ
災害時にトイレとして簡単に使えるものが「大人用紙おむつ」です。
おむつとしてはもちろん、廃液などを吸収させて捨てることもできますし、未開封状態であればクッションの役割も果たせます。
簡易トイレがあれば十分ですが、紙おむつはあると便利ですので、1パックでもいいので用意しておくといいでしょう。
トイレでの必需品「トイレットペーパー」
有事の際、避難しても避難しなくてもトイレは必須です。
その時に必要なのが「トイレットペーパー」です。
簡易トイレを使う場合は柔らかい紙なら何でもいいですが、流すならトイレットペーパーは必須でしょう。
避難先の仮設トイレにトイレットペーパーがなかったりする場合もありますので、必ず持っていきましょう。
最近は、〇倍巻きと謳う商品が出てきて、スペースを取らずに長く使うことができるものが発売されているため、〇倍巻きのトイレットペーパーを利用することをお勧めします。
トイレットペーパーはお尻を拭くだけではなく、ペーパー類の代用として使えるため、あって困りません。
家に備蓄しておくのはもちろん、持っていけるだけ持っていきましょう。
7、防暑・防寒対策
最近の日本の夏はとても暑く、気温が30℃を超える日が続くことがあるため、その様なときに戦争や災害で避難生活を余儀なくされたとき、防暑対策が必須ですし、真冬に避難生活を余儀なくされたときにも防寒対策が必須です。
最悪、命に関わる事態となるかもしれませんので、どのような対策があるか知っておいた方がいいでしょう。
防暑対策
もしポータブル電源などの電源があるなら、ポータブル冷蔵庫を使って保冷剤を冷やして使うことができますし、ハンディファンやポータブルクーラーで涼をとることもできます。
もし電源がないなら、冷却スプレーや冷えピタなどの消耗品で代用しましょう。
標高の高い山にキャンプを張ることも暑さ対策になります。
水辺は大雨などの時に危ないので注意です。
キャンプの際はあなたのスマートフォンに電波が届くところを選びましょう。
◎ポータブル冷蔵庫
持ち運びが楽なタイヤ付きのものがおすすめです。
防寒対策
もしポータブル電源などの電源があるなら、充電式湯たんぽや充電式カイロ、ハロゲンヒーターなどで暖を取ることができますが、もしないなら、ホッカイロやお湯を入れる湯たんぽなどで代用しましょう。
そして秋~冬の間であれば防寒ジャケットやダウン、防水手袋などは必須です。
焚火をしていい場所なら、チャッカマンやファイヤースターターなどで火をつけて焚火をしましょう。
焚火の際は周りに迷惑にならないよう、注意を払いましょう。
避難生活で怖いのは周りの人ですので、なるべく軋轢が生じないように心がけましょう。
◎ファイヤースターター
8、拠点の確保
自宅

戦争や災害の被害を受けたとき、自宅を拠点にできるのは幸運なことです。
例え断水、停電していたとしても、雨風をしのげる場所があるのは心強いです。
まずは家の状況を確認し、外の状況を把握し、テレビやスマートフォン、パソコン、ラジオなどで情報を集め、水や食料などの必需品を買いに出かけましょう。
手分けができるなら、家の状況を確認をしてテレビやスマートフォンなどで情報を集める係と外の状況を把握しつつ買い出しに行く係とに分かれて行動しましょう。
もし周囲が悲惨な状況の場合、安全を確認した上で避難所に行って情報を集めましょう。
支援物資などの情報をどこで受け取るかなどが分かるかもしれません。
もし戦争となった場合、空いている敷地があればいざという時の防空壕を作ることも検討しましょう。
核シェルター(地下シェルター)
NPO法人日本核シェルター協会によると、2014年時点での各国の人口あたりの核シェルター普及率は、スイス、イスラエルが100%、ノルウェーが98%、アメリカが82%、ロシアが78%、イギリスが67%であるのに対して、日本はわずか0.02%という調査結果がでています。
これは日本に戦争の脅威が無い期間が長かった結果だと思いますが、今はもうそういう時代ではなくなってしまい、核戦争の脅威が現実味を帯びてきています。
日本はアメリカ、中国、ロシア、北朝鮮という4ヵ国の核保有国に囲まれており、軍事的緊張が高まっているからです。
ですが核シェルターをただ設置すればいいという訳ではなく、そこには「生存率アップ」のための工夫が必要となります。
核シェルターはその名の通り、核ミサイルが落とされたとしてもできる限り長く生き延びることができる避難空間のことです。
そのため、放射線対策、入り口が瓦礫で塞がれてしまった場合の対策、トイレやごみ対策、換気、物資の保管、そして居住性が重要になってきます。
出来得るなら、核シェルターは重量コンクリートと鋼板や鉛板などを組み合わせることによって放射線を可能な限りカットし、塞がれた場合のことを考えて入り口を2ヵ所に作るか重量物も押し上げて出られるようにし、高性能換気フィルターによって外から入ってくる有害物質を遮断して室内の汚れた空気と入れ換え、考えられたトイレスペースやごみ置き場が確保され、食料などの物資を適切に保管でき、スマートフォンやパソコンなどが使え、ストレス軽減のためにそれなりに快適な居住空間であることが大切です。
核シェルターではなく災害対策の地下シェルターなら、放射線対策や高性能過ぎる喚起システムは必要ないのではないかと思います。
最近は戦争や大災害が近いと思われているのか、核シェルターの問い合わせが急増していると言われています。
あなたが核シェルターを設置することを決めたとしても、それを家族以外の人に知られてはいけません。
噂はすぐに広まりますし、いざという時、それを知った人達があなたの核シェルターに殺到するでしょう。
殺到した人達が理解を示さないこともあり、その時、あなたや家族に危険が迫るかもしれません。
避難所

家が何らかの理由で居住できなくなったとき、体育館などの避難所に避難することを余儀なくされるかもしれません。
避難所では簡単な仕切りで区切られた場所を割り当てられ、他に避難してきた人たちとともに共同生活をすることになります。
雨風にさらされないことはとてもありがたいことですが、床で寝て周囲の目を気にしながらの生活になるため、快適とは程遠いものになります。
ですが避難所は同じく避難している人たちがいるため情報を得やすく、支援物資が届きやすいというメリットがあります。
そのため、周囲の安全を確認した後は避難所にまず駆けつけて情報を得ましょう。
もし核ミサイルでの攻撃だった場合は、テレビやインターネットなどで情報を得た上で、放射線物質から逃れるように避難しましょう。
その場合は県外にも避難所が設置されているはずです。
車中泊

もし家や避難所が倒壊の恐れがあるなどで利用できない場合があり得ますし、避難所ではペットと避難者は別の部屋で過ごすなどの場合が多いです。
その場合、車中泊という選択肢があります。
車中泊の場合、ガソリンや電気が続く限りエアコンが利用できますし、危険が迫ったらすぐに出発できるというメリットがあります。
大人数の場合は寝心地は悪いかもしれませんが、一時的な避難場所としてはプライバシーは守られますしそれなりに快適でしょう。
旅行に行く際にホテルなどで泊まるのではなく、練習のために車中泊をしてみると車中泊であなたに必要なものが見えてくると思います。
野外キャンプ

季節にもよりますが、上記の車中泊ではなく、キャンプ慣れしている人はキャンプ用具を持って野外キャンプもいいでしょう。
野外キャンプをする場合は必ず治安の良い(襲撃されない)場所を選びましょう。
キャンプ用具はそのまま防災用具となる場合が多いですので、キャンプを選択肢に入れたいと思っている人はキャンプ用具を購入して練習しましょう。
何事もまずは経験して気づいたところを改善し、足りなかったところを補うことが大切です。
9、その他に備えておくべき必需品
現金

最近はキャッシュレス決済が普及し始め、現金を持つ人が徐々に少なくなってきています。
ですが、戦争や災害の時、キャッシュレスだと決済ができないシーンが出てきます。
地震直後は特に停電などによりATMも使用できできず、電子決済対応のレジなどが作動しないことが想定されます。
そしてあなたの状況によっては、水や食料、衣類、ガソリン代や公共交通機関を利用するための交通費、ホテルなどへの宿泊費が必要となるかもしれません。
家から離れた場所にいて、まず家まで帰らなければならない状況なども想定されます。
財布の中には常に1万円以上入れておき、家にもあなたの懐事情に合わせた緊急時資金を貯めておくといざという時に使えます。
すぐに避難しなければならない状況の時を考え、保管しておく所は手提げ金庫やポーチなどのすぐに持っていけるものの中がいいでしょう。
身分証明書

家から離れることを余儀なくされる場合、身分証明書は必ず持って行ってください。
避難先の銀行からお金を下ろす時や罹災証明書、届出避難場所証明書などの行政書類を請求するときに必要になります。
運転免許証と健康保険証があればほとんどのシーンに対応できるでしょう。
近い将来、マイナンバーカード1枚で運転免許証と健康保険証の役割も果たせるようになるということなので、その時はマイナンバーカードを持っていきましょう。
そして、もし戦争の場合はパスポートも持っていきましょう。
海外に逃れなければならない事態になった場合、パスポートの有り無しがあなたの命の分水嶺になるかもしれません。
情報端末など
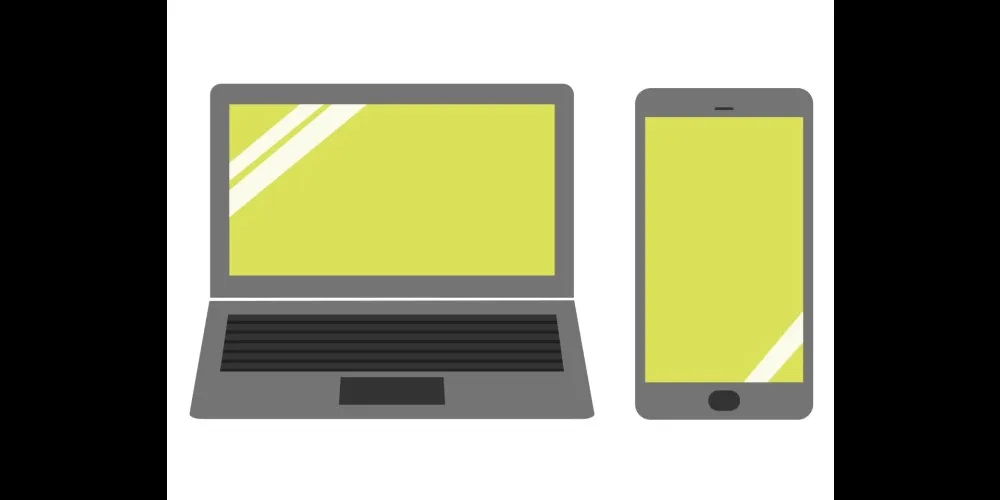
家から離れることを余儀なくされた場合、スマートフォンやノートパソコンを持ち出しましょう。
用意してあるなら携帯用ラジオもあると災害情報を複数のチャネルから得ることができます。
災害情報は水と食料と同じくとても重要です。
情報の有る無しが生死を分けることもあります。
ただしインターネット掲示板などの書き込みなどを簡単に信じてはいけません。
情報元を確認することが大切です。
◎ポータブルラジオ(防災用)
こちらの製品はUSBやAC充電だけではなく、手回し充電や発電量は少ないですが太陽光発電にも対応しているため、電源のない場所でも継続的に使うことができます。
LEDライトもついているため、夜中にラジオを聴きながら何か作業をするのにも便利です。
商品画像だと大きく見えますが、実際はスマートフォンと同じくらいの大きさで、手の平サイズです。
筆記用具
筆記用具は直接命に関わるものではないですが、とても重要です。
連絡先、人から聞いた情報、テレビやインターネットでの情報を書き留めることができます。
重要情報や出来事を記録できますし、書き留めた情報を後で検討して行動できますので、行動がより正確になり無駄が無くなります。
そのため、最低でもペンや鉛筆、消しゴム、鉛筆削り(小型のもの)、油性マジック、ノートやメモ帳を備えておく必要があります。
鉛筆?と思うかもしれませんが、災害時だと鉛筆は優秀です。
紙以外にも書けますし、濡れたとしても乾かせば使えます。
ボールペンのように急に詰まりなどで使えなくなることもありません。
そしてノートやメモ帳が尽きたときでも、いらない情報を消しゴムで消して使えます。
できるなら、すべて水に濡れても使えるものが望ましいですが、気を付けて使うなら普通のもので構いません。
ペンや鉛筆、消しゴム、鉛筆削りは袋タイプのペンケースに入れ、ノートやメモ帳を入れておく袋の中に入れて一緒にしておきましょう。
洗濯用具
洗濯機が使える場合は問題ありませんが、停電時で洗濯機が使えない場合や避難生活が長期に渡る場合、衛生を保つために洗濯することを考えなければならないときが来ます。
水が全く使えない時は、毎日着替えながら除菌消臭スプレーをかけて天日干しするようにすれば臭ってくるまでの時間が稼げます。
水が使えるときは手もみ洗いをしましょう。
手もみ洗いできる大きさの丈夫な袋に水と洗剤と洗濯物を入れて揉むだけです。
洗濯の時間がない時は漬け置き洗いで構いませんが、数日に1日は手もみ洗いをすることをおすすめします。
◎どこでも洗濯グッズ
こちらの製品は水と洗剤を入れて振るだけで洗濯ができるランドリーバッグです。
ランドリーバッグは10リットルくらいのものがおすすめです。
5リットル以下だと小さすぎ、20リットルくらいのものになると振るのが大変で袋の耐久性に問題が出てくる場合があるからです。
10リットルはTシャツ3枚分くらいを洗えますので、1~2人の時はこれ1袋で十分ですが、3人以上の時は2袋以上用意して、複数人で洗いましょう。
折りたためばスペースを取らないため、持ち運びも楽です。
作業用具
作業というのは、DIYや瓦礫をどかしたりする大きなものだけではなく、電池交換や眼鏡などのネジ止めのときにドライバーを使ったりする小さなものも含まれます。
家が拠点として使える状態であれば、家にある工具を使えますが、避難生活を余儀なくされる場合は危険度に応じて最低限の工具を持っていきましょう。
最低限必要なものはハンマー、ドライバー一式、モンキーレンチ×2です。
もしDIYをしたり瓦礫をどかしたり、穴を掘ったりするなら、のこぎり、メジャー、レンチ一式(同じセットを2セット)、防災斧やバール、折り畳み式スコップがあるといいでしょう。
もし野外へ避難しなければならない事態になった場合、折り畳み式スコップがあればテント設置時の整地や防空壕を掘ることにもも役立つでしょう。
穴を掘ってトイレにすることもできます。
レンチ類が2セットなのは、両側から締め付ける状況の時に必要だからです。
周囲が危険で治安が悪いなら、避難時でも防災斧やバール、スコップなど武器となるものを持っていくことをおすすめします。
そして作業をするときに大切な手を保護するために軍手を着用しましょう。
軽作業の時は普通の使いやすい軍手でいいですが、危険な作業をするときは厚手の軍手をして作業しましょう。
◎斧、のこぎり、折り畳み式スコップが入ったセット
水を貯める容器
被災生活時で断水した場合、水の確保は最重要事項です。
備蓄水だけでは足りず、給水車や湧き水の利用などで外から水を得てくる時がありますし、真冬に外に暖かい飲み物を持っていく時があるかもしれません。
そのような時に水を運ぶための容器が必要となってきます。
給水車などから水を貰って運ぶときはウォータータンクやポリタンク、ペットボトルが必要でしょうし、暖かい飲み物を持っていく際は水筒が便利です。
水筒は人数分用意しましょう。
バッグやリュック
もし避難生活となった場合、生活用品や小物、衣類やタオルを入れて持ち運ぶ必要がありますし、車を乗り捨てて歩いて移動しなければならないことになるかもしれません。
そのときにボストンバッグやリュックが活躍します。
ボストンバッグはあなたが持ち運びできる大きさのものでなるべく大きいものを用意しましょう。
リュックは持つ人の体格に合わせて用意しましょう。
それぞれ防水のもので、ポケットが多いものを選ぶと便利ですが、いつも使っているもので大丈夫です。
ティッシュ類
ポケットティッシュ、BOXティッシュ、ウェットティッシュなどのティッシュの類はあって困るものではありません。
ウェットティッシュとBOXティッシュを少し多めに備蓄しておきましょう。
ウェットティッシュはおしり拭き用のものだとお年寄りや子供、肌の弱い人にも使えます。
ですが、水が制限される場面でトイレの後に手を拭いたりするときや物を清潔に保ちたいときのためにアルコール除菌ウェットティッシュも用意しておきましょう。
避難を余儀なくされた場合、ポケットティッシュがあったら空いているポケットに入れ、車の空いているスペースにウェットティッシュやBOXティッシュを突っ込みましょう。
ポリ袋
ポリ袋はもちろんゴミを入れるのに使えますし、穴を開けて着たり、新聞紙を丸めて入れて足や手を突っ込めばちょっとした防寒対策グッズにもなります。
そして簡易トイレが無い時に便座にかぶせて中に新聞紙を丸めて入れれば簡易トイレの代わりにもなります。
トイレに使用する際は中が透けて見えないもので防臭タイプがおすすめです。
ポリ袋は多めに備蓄しておくといいと思います。
その他
その他は、数日間のキャンプや車中泊を想定した場合のあなたにとっての必需品です。
中には病気や障害をお持ちの方、女性や子供、お年寄りの方もいるでしょう。
なるべく事前にキャンプや車中泊の練習をして、必要だと思ったものや足りなかったものなどをリストアップしていきましょう。
練習の場合はレジャー感覚ですので、キャンプや車中泊は意外と楽しいですし、失敗したとしても経験だと思えます。
10、被災生活時の注意点
もし周囲が深刻な状況となった場合、もしくは将来深刻な状況となる可能性が少しでもある場合、あなたが現金や物資などを持っていることを知られてはいけません。
人はお金や物がある場所に集まり、正当不当問わず、それらを手に入れようとするからです。
周囲の人を観察し、周囲の人に溶け込むように振舞いましょう。
何かあったとしても軋轢を生じさせて敵を作るようなことはやめましょう。
一番頼りになるのは人ですが、一番怖いのも人です。
11、最後に
戦争や災害などで被災したときは様々な状況に見舞われます。
その様々な状況に対応するために備えられるだけ備えておくとあなたの生活を安定させる時間を与えてくれますが、備えは時間とともに失われ、いつか尽きて終わりの時がきます。
そのような状況にならないためにも、与えられた時間を無駄にせず、その時間を引き延ばすよう考え、行動していきましょう。
必要な物、役に立つものは紹介しましたが、すべてを用意するのは難しい人が多いのではないかと思います。
あなたには何が必要なのか、そして優先順位を考えて取捨選択していきましょう。
